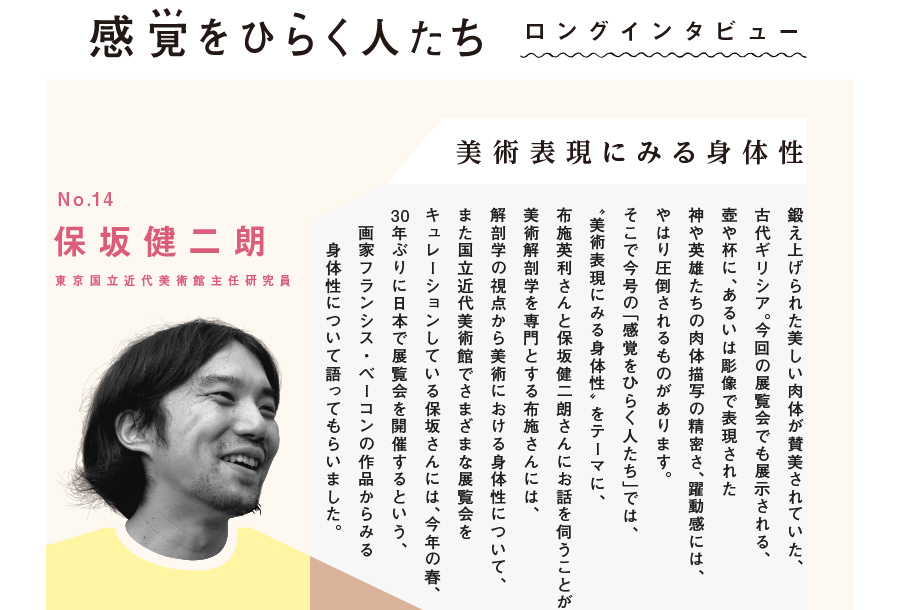フランシス・ベーコンが
捉えた人間の身体
── 保坂さんは戦後イギリスを代表する画家、フランシス・ベーコンの大規模な個展をキュレーションされていますが、彼は人間の身体をどのように捉えていたのでしょうか?
フランシス・ベーコンは古代ギリシアとは全然違う、独特のアプローチで身体表現に迫ったアーティストです。彼の身体の捉え方は、20世紀における現代美術の中でさえも特異なものではないかと思います。その前提のもと、現在、僕がキュレーションしている『フランシス・ベーコン展』(2013年3月8日〜5月26日、東京国立近代美術館)では、彼が人間の身体をどう捉えたのかに焦点をあてて、年代ごとに3つの章に分けて探っていくことにしました。
最初の章、1940〜50年代の作品群には「移りゆく身体」というタイトルをつけました。この頃彼はカーテンか細い帯がたくさん垂れ下がったような空間の向こう、あるいは手前に人間がいる、という絵を何枚も描いています。亡霊のような身体は消えていくようでもあり、現れてくる途中のようでもある。またこの頃繰り返し描かれたモチーフに《叫ぶ教皇》があります。生まれたときは普通の人間だったのに、最後は神にもっとも近い存在として死ぬというのがカトリックの頂点に立つ教皇の特徴です。そんな存在が叫んでいるということは、その瞬間だけ、彼は人間に戻っていることになる。ベーコンが描く教皇は、聖なる存在へと移り変わったはずの人間が、叫ぶことで、再び俗なる人間に還っている、そんな「移りゆき」の状態にあるといえるんです。
── 第2章には「捧げられた身体」というタイトルがついていますが、これはどのような意味でしょうか?
第2章では1960年代に描かれた作品群を扱っています。この頃描かれた絵にはソファやベッドなど、日常生活で見慣れたシンプルな家具に身体が置かれています。その身体は、50年代までの作品とは異なり、絵具の確かな物質性がありつつも、不自然なポーズをとっているのが特徴です。ぽんと置かれているその姿は、何かに向けて差し出されているように、あたかも犠牲になっているように見えないでしょうか。さかのぼって、ベーコン自身がデビュー作としている《ある磔刑図のための3つの習作》(1944年)という作品では、キリストの磔刑がモチーフになっています。
1909年にアイルランドに生まれたベーコンは、幼少時にアイルランド独立戦争を、イギリスに移ってからは第一次世界大戦と第二次世界大戦を体験しました。多感な時期に戦争の不条理を見つめた彼は、20世紀では、キリストが磔になるという形での犠牲では救われることがないのだと実感したんだろうと思います。そして、この時期に描かれた身体には、“現代における救いとは何か、そのとき犠牲とはどのようにあるべきか”というベーコンなりの考えが込められているように感じているんです。
── ベーコンの作品には同時代の演劇の影響も指摘されています。
アイルランド出身の劇作家、サミュエル・ベケットの演劇に見られるシンプルな舞台美術は、第2章「捧げられた身体」で出品される、整理された室内空間を描いた作品と並行関係にあると考えられます。ベーコン自身は影響を受けたことを否定していますが、同時代で同じアイルランド出身の作家を知らなかったはずはないと思われます。
1970年代以降の作品を中心にした展覧会の第3章「物語らない身体」には、登場人物の数が増えたり、鏡が描きこまれたりした作品が並びます。こうして画面は複雑になっているのですが、そこに物語は感じられず、その意味で身体は、行き場を失っています。当時盛んになっていた、不条理演劇やポストモダン演劇、あるいはポストモダン文学も明快な物語を欠いた表現であり、このころのベーコンの絵画との同時代性を感じさせます。
第3章に出される絵には足の上に直接、頭がつながっているかのように見える身体が描かれたものもあります。それらは、現実とはさまざまな意味で暴力的であるというような、現代の身体が置かれている状況を直接的に表現しているのではないかとも思います。
絵画でしかできない、
身体表現の追求
── ベーコンは写真を元に描いていたと言われていますが。
ベーコンの没後、アトリエに残っていた資料の解析が進んでいますが、その結果、ベーコンが、友人に撮影を依頼した写真をくしゃくしゃにしたり、切り抜いたり、さらにはそれらをクリップで留めたりして、それをトレースして身体を描いていたことがわかってきました。
現代では写真の登場によってポートレイト絵画の役割は失われたといわれていますし、ベーコンもそれを認めています。一方でピカソらキュビスムの画家たちが写真に線を引いたりして描いていたこともわかっていますが、その方法論も行き詰まってしまい、人間性や身体性を回復することができなかった。そこでピカソは身体性を回復させるべく、シュルレアリスム的な表現を経て新古典主義に向かったわけですが、新古典主義は文字通り、古代ギリシア・ローマ時代の表現への回帰ですから、現代の身体表現とはなりえない。ベーコンはそういった状況を踏まえた上で、戦後という現代において絵画でしかできない身体表現とは何か、人物表現にはいかなる方法があるのかを模索したわけです。そのときに、写真の性質を逆手にとって利用しているのが、ベーコンのおもしろさだと思います。
── 保坂さんは以前、ベーコンの描く身体と、東洋における身体観との類似性を指摘されたことがありますが。
ベーコンの描く肉体は、ときに軸線がなくなったり、ときに輪郭が消滅して二つの身体が溶けあったりします。そうした「肉体」は、往々にして、できる限り床に近づこうとしているように見えます。西洋の一般的な肉体表現では輪郭が溶けることはありませんし、西洋のダンスでは、直立したりジャンプしたり回転したり、とにかくできるだけ、重力から離れようとするのが特徴です。それとは逆の方向を向いたベーコンの身体観は、西洋の身体観とは異質なものであり、むしろ、土方巽たちが始めた日本の舞踏(Butoh)に近いのではないかと僕は思っているんです。舞踏では飛び上がったりはせず、床をのたうち回るような動きを多用します。また二人の人が組んず解れつするという動きもよく出てくる。土方のスクラップブックにはベーコンの絵を見つけることができますし、上演はされていませんが、ベーコンを題材にした舞台を構想していたこともわかっています。「床に寝そべってけいれんする」という動きに「ベーコンのポーズ」というキーワードもつけていました。
今回のベーコン展では、彼の絶筆をもとに作られたドイツのバレエ振付家、ウィリアム・フォーサイスが登場する映像インスタレーションが出品されます。加えてダンスまたはパフォーマンスによるイベントも考えています。バレエやダンスを通して肉体の可動範囲やコントロールの限界を知ることで、生身の人体とベーコンが描いた身体とをより詳細に比べることができる。そう感じています。
── ベーコンの絵では複数の人物が登場していても、暖かみよりもどことなく冷ややかなものが感じられます。
ベーコンは、抱きあう二人の人間をよく描いています。身体を密着させるこの行為は人間にとって根源的なコミュニケーションであり、輪郭が溶けあう二人の人物像という姿には、「肉」として他者と同一化したいという欲求が感じられます。それが現実世界では不可能であることを考えると、逆にその絵からは、ただ一人の人物像で描かれる直接的な孤独よりも、強い痛みを伴った孤独が感じられるような気がします。
── ベーコンの身体表現は他の誰にも似ていないということですが、彼に匹敵するほどの独創的な身体表現を成し遂げたアーティストはいないのでしょうか?
ベーコンの対極にある同時代の芸術家として、アルベルト・ジャコメッティがあげられると思います。ベーコンの描く身体が肉感的で触覚に近いものであるのに対し、ジャコメッティの彫像は、彫刻であるにもかかわらず、どちらかというと視覚的、観念的です。ただ二人とも、いかに孤独を表現するかを追究しているという意味において、実存主義的な立場をとっている。その方法が両極に分かれているわけですが、どちらも極めて20世紀的な身体表現を追究した芸術家だったと、僕は思っています。